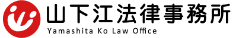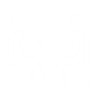遺言は形式面にまったく問題がなくても常に有効とされるわけではありません。作成時に作成者が遺言能力を欠く状態にあったとして遺言が無効とされることがあります。自筆証書遺言はもちろんですが,公証人が関わって作成する公正証書遺言であってもまれに遺言能力を欠くとして無効となることがあります。
遺言能力とは何なのでしょうか。
民法では遺言を作成できる能力,遺言能力に関しては明確には定義していません。そのため諸説あり,定説はありません。結局のところ,裁判実務では遺言能力については遺言の内容を含む様々な事情を総合して判断しているようです。
特にポイントとなるのは,遺言者の年齢,健康状態,遺言時前後の言動,遺言の作成過程,日頃の遺言についての意向,受贈者との関係,遺言の内容の難易,遺言内容の合理性などです。医学的判断を尊重しつつ,最終的には裁判所が法的判断を行うべきと考えられています。
遺言能力の有無に関して特に問題となるのは認知症です。一時的なせん妄や加齢に伴う認知機能の低下では遺言能力を否定されることはあまりありません。しかし,認知症の場合には遺言能力が否定されるケースが出てきます。また,同じ認知症の中でも,症状が「まだら」である血管性認知症では遺言能力は認められやすく,脳全体がダメージを受け全般性の認知障害があるアルツハイマー型認知症は病状が進行していると遺言能力が認められにくいという違いがあります。
認知症の機能障害の大まかな把握のために改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)が活用されることがあります。認知機能の状態を機材を使わずに短時間でテストできるので広く使われています。30点満点で評価し,1桁なら遺言能力は否定することが多いようであり,20未満なら他の要素次第と,HDS-Rの結果は遺言能力の判定に多くの裁判例で参考とされています。
遺言能力は様々な事情から判断され,認知症の病状は大きな判断要素となることは前述のとおりですが,必ずしもそれのみで判断されるわけではないことに注意が必要です。
重度の認知症(HDS-Rで1桁)でも遺言の内容がシンプルであり,当時の状況から合理的な内容であったため遺言能力を肯定した裁判例もあります(京都地裁判決H13.1.10)。
このように遺言能力は病状のみから単純に決まるものではなく,遺言の内容などにも影響を受けます。
遺言能力の有無が後々紛争になることも多く,有効性が疑わしい遺言の存在は深刻なトラブルを巻き起こします。遺言を作成する際にはぜひ当事務所にご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所