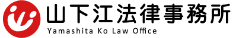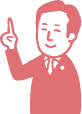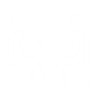目次
未成年の子がいるなら要注意!遺言がないと困る理由
皆さんは遺言を書いたことはありますか?おそらく多くの方は「NO」と答えるでしょう。
- 「揉めるような財産などない。」
- 「自分はまだ若いから書く必要がない。」
- 「そんな大事なことを今決められない。」
そんな声が聞こえてきそうです。
しかし、特に小さいお子さんがいるご家庭では、年齢に関係なく遺言の作成を強くおすすめします。
たとえば、夫婦と未成年の長男・長女の4人家族で、夫が不慮の事故で亡くなったとします。遺言がなければ、夫の財産は妻と子2人が法定相続人となり、遺産分割協議を行い、相続することになります。
夫名義のマンションがある場合、名義を妻に変更するには、妻と子2人による遺産分割協議が必要です。
しかし、ここで問題が生じます。未成年の子の代理人として妻が協議に参加することはできません。
なぜなら、妻自身も相続人であり、子どもたちと「利益相反」の関係にあるからです。(※補足:民法第826条により、利益相反がある場合、親権者は子の代理人になれません。)
このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。この手続きは時間も手間もかかり、精神的な負担も大きくなります。
もし、夫が「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を残していて、遺言執行者も定められていれば、遺産分割協議や特別代理人の選任は不要でした。(補足:ただし、子どもたちの「遺留分」を侵害する場合は、後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法第1046条))
今回は具体的に遺言書の文章を提案しておきます。
上記ケースで妻にすべて任せるつもりであれば是非参考にしてください。
便せんなどに全文を手書きで書いて、最後に自署し、押印してください。日付は遺言を作成した日を書いてください。誤記があるときは一から書き直す方が賢明です。
遺言書
第1条 遺言者は、不動産、預貯金など相続開始時に所有する財産のすべてを遺言者の妻〇〇(昭和×年×月×日生、以下「〇〇」という。)に相続させる。
第2条 遺言者は、〇〇を遺言執行者に指定する。遺言執行者は、遺言者の預貯金を解約して払戻しを受けること、遺言者のその余の金融資産等を換価して換価金を受領すること、不動産について必要な登記手続を行うことなど、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。遺言執行者はその任務を第三者に行わせることができる。
令和×年×月×日
住所
氏名 印
参考になりましたでしょうか。
事情によってはもう少し複雑な内容にする必要があるかと思います。
2020年からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も始まりました。この制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要となり、遺言の紛失や改ざんのリスクも軽減されます。
遺言は「揉めないため」だけでなく、「家族を守るため」の大切な手段です。内容や形式に不備があると、遺言が無効になることもあります。「遺言を作ってみたい」と思った方は、ぜひ専門家にご相談ください。